<< 後編>>
MQA-CD開発者が設計したMQAデコーダー搭載機
Meridian218を聴く(前編)
文:橋爪 徹

今や最もポピュラーな音楽聴取手段は言うまでも無くYouTubeだ。しかし日本ではコンパクトディスクの人気もまだまだ衰えず最近のレコード協会の調査でも両者は2トップを争っている。音楽を手元に残るディスクとして所有したい、という日本の音楽ファンやオーディオファンの思いは根強いものがある。
一方で音楽好きの間でずっと気になっている存在がハイレゾだろう。とはいっても、PCの取り扱いやネットワークの設定方法など、何やら難しそうで踏み切れない、という方も少ないと思う。
そんなあなたに朗報だ。今までのハイレゾより、ぐっと簡単に楽しめるMQA-CDという新しいメディアが誕生したのだ。新しいメディアと言っても、普通のコンパクトディスクとして再生できる。
そしてMQAデコーダー搭載機によってハイレゾの音質も楽しめるとあって音楽好きやオーディオ愛好者の中で話題になっている。
Meridian 218(以下、218)はお手持ちのCDプレーヤーを接続してMQA-CDをハイレゾ音源として楽しむことができる優れモノだ。筆者の自宅、防音スタジオに届いた218は驚くほどコンパクトだった。幅20cm、奥行きは15cm、厚みも約4cmしかない。リア側は入出力端子がびっしり満載だが、フロントパネル側はスイッチ類を排したフラットフェイス。iPhone、iPadの専用アプリにすべての操作機能を集約させている。
CDプレーヤーと218との接続は2つの方法がある。光デジタルケーブルを使うか、あるいは同軸ケーブルを使うかだ。CDプレーヤーには、いずれか一つは装備されていることが多い。今回、筆者は同軸ケーブルを選択した。(接続や操作の詳細はこちら)
218はMQA-CDのマスタークオリティの違いを如実に再現
本機は想像していたよりずっと小さかったしデザインも超シンプルだ。正直言って、第一印象として全くもってオーディオライクな雰囲気はなかった。しかしセッティングを終えて実際に音を出した瞬間、それはガラッと変わった。
まずは MQA-CDから聴いてみた。「ハイレゾCD」と銘打って名盤を続々とリリースしているユニバ ーサルミュージックの「ハイレゾCD 体験サンプラー」 CDと MQA-CDの 2 枚1組で 1,000 円ポッキリ。邦楽、クラシック、ジャズとロック&ポップスと4種類が発売されている。
このサンプラーは、国内で起こしたSACD用の DSD マスターをPCM352.8 kHz/24bit に変換後、MQA エンコードを行っている。
なお、CDの方は普通のポリカーボネート素材。MQA-CDの方には、信号の読み取り精度が高いUHQCDが採用されている。言ってみればピンとキリを比較しているようなもの。従って以下は純粋なMQAデコードの違いだけではなくて、ディスク素材の違いも含めた比較評価となることを最初にお断りしておきたい。
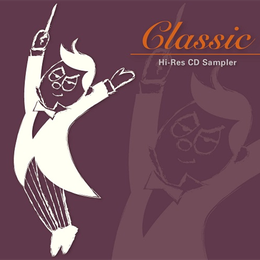
それではまず、クラシックからベートーヴェン「運命」を聴く。
CDでは、少しダイナミックスに窮屈さを感じたが MQA-CDを再生すると、途端に音場が奥にも左右にも広がった。コンサートホールの臨場感が別次元の領域に達している。218では CD プレーヤーからの信号も FIFO メモリ(ファーストインファーストアウト)使った独自のクロック回路を採用している。
オーディオマニアの間では、クロックのタイミング精度を上げることで、その音と響きの織りなす空間表現力がぐっと高まることが知られている。ジッターノイズの大きいディスク再生で、その効果が特に有効であることを確認できた。以下、CD と MQA-CD を比較しながら進めていく。
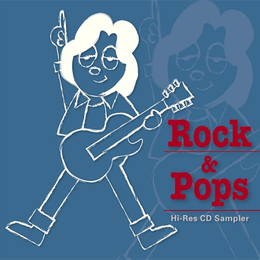
続いて、ロック&ポップスからオールマンブラザーズバンドの「ユー・ドント・ラブ・ミー」
MQA-CD では混濁していた音場の見通しが良くなる。例えばキーボードの音に埋もれて聞こえにくかったギターのレフが右チャンネル側に存在することに気付けるようになったり、ライブハウスの演者の立ち位置がリアルに想像できるような音像定位の改善にも目を見張るものがある。ドラムのキレの良さが上がり楽曲全体がリズミックに躍動。聴いていてライブに前のめりになれる、没入型のサウンドになったといえる。
ライブ会場で一発ミックスしたと思われるラフな音調も含め、リアリティがあって良いと思えた。CDに戻してみると、鮮度を失った楽器音が窮屈な音場でケンカしているような印象だ。一度 MQA を耳にしたら二度と CD には戻れない。
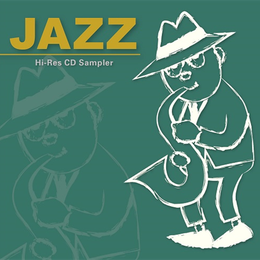
ジャズからは、アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズの演奏で名曲「モーニン」
楽器のディテールがハッキリと見えるようになった。トランペットの湿った空気感や、ドラムの響きなどリアルになる。また、MQA-CDの方が明らかに録音がアナログテープであることが分かりやすい。ヒスノイズも聞きとれるほどに聴感上の S/N 比が良くなった。
総じて MQA-CD では、その圧倒的な情報量の多さで再生しているメディアがCDであることを忘れさせてくれる。218 はスペックとしては 176kHz のフルデコード処理だが、メリディアン独自の精密なアップサンプリング技術の独自ノウハウを窺うことができた。
続いて続々発売されている各レーベルの MQA-CDもチェックしていこう。

OTTAVA(RME Premium Recording)から『Contigo en La Distancia』~遠く離れていても~ より「Chorinho Pra Ele」
本作は、第 24 回日本プロ音楽録音賞・ハイレゾリューション部門において最優秀賞を受賞している。UNAMAS レーベルの代表 Mick 沢口氏が録音エンジニアで、MQA-CD マスターは176.4kHz/24bit。
比較的近い距離のマイクで録ったバイオリンの“ダイレクトな音像”と、少し離れて置いたマイクで録ったと思わる“音場型のピアノ”が対照的だ。ホールに響き渡るピアノ音の美しさ、余韻の階調がとてもピュアで、真に迫るトランジェントを感じさせる。沢口氏の録音とミックスによって、ガット弦のバイオリンがその荒々しいまでの音色を保ちながら、見事にピアノと調和して耳に心地よいバランスをキープしている。沢口氏の高い手腕が光る作品だ。
南佳孝の Dear My Generation から「柔らかい雨」
昭和の味わい豊かな大人の音作りが特徴の作品。解像度の高いマイクが選別されて、南佳孝の声の色気や潤いがしっかり感じとれる。2番から入ってくるピアノの残響は階調豊かな減衰の仕方が美しく印象に残った。普通のCDではなかなか体験できない贅沢な味わいだ。マスタリングはグラミー賞2回受賞の世界的なエンジニア GOH HOTODA。MQA-CD マスターは 88.2kHz/24bit。

レベッカ・ピジョンの The Raven から「Grandmother」
最初のボーカルの第一声が聞こえたとき、ウワッ!となった。情熱的なボーカルの抑揚がライブのようなリアリティを放っている。
後半に掛けて音数がどんどん増えていくが、それでも一切混濁なく各楽器がちゃんと調和しながらも存在感を保っているのが素晴らしい。序盤からギターを叩いてリズムを取るのだが、音の立ち上がりや立ち下がりの鋭さが真に迫っており「そうそう、こういう音!」と感動した。
単に音像がクリアになるだけではこうはいかない。MQA の時間情報の解像度アップは生音の再現性を根底から支える重要なバックグラウンドなのだ。名門チェスキーの 1994 年のアナログの録音だがその鮮度の良さは不滅。MQA-CD マスターは176.4kHz/24bit。

オクタビアより名倉誠人の涙と祈りから「紅 (マリンバ、ヴァイオリン、ピアノのための)」
ホールの高さが出音から見えてくるのはすごい。例えば、音が一瞬静かになったとき、演奏し始めに起こるかすかな物音も、ホールの右奥の方で鳴っていると位置関係まで分かる。そして、なぜだかアナログっぽい音がする。DSD の独特の音色とも違う。デジタル録音としての俊敏さや正確さは維持しながらも、現場の音をそのまま聴いているような臨場感がある。MQA-CD マスターは176.4kHz/24bit。

最後にボブジェームスの最新作 Espresso から「Boss Lady」
まず、心地よいのは密度のあるベース音。ハイレゾならではのリッチさである。CDだともっとアッサリして薄くなるはずだ。また奏者の呼吸のダイナミズムが伝わってくる。今そこで演奏されているような躍動感を味わえる。MQA-CD マスターは 88.2kHz/24bit だ。
以上、話題のMQA-CDをMeridian218で聴いてみた。
『MQAは決して悪いマスターの音を改善するものではない』、と Unamas レーベルのミック沢口さんは常々仰せになっている。確かにMeridian218でこうして、各レーベルを聴いてみると MQA-CD はマスタークオリティの素性をよりストレートに再現させるものだった。
後編では、メリディアンがディスク再生にこだわって開発してきたユニークなDSP(デジタル音声処理)技術を簡単に紹介しながら、普段聴き慣れている筆者愛聴のCDなども218でチェックしていく。




